車を選ぶとき、「プジョーの小さい車」が気になるという方は少なくありません。特に日本の都市部では取り回しやすさや駐車のしやすさが重要視されるため、プジョーのコンパクトモデルは注目されています。
では実際に、プジョーで一番小さい車はどれ?と疑問に思う方に向けて、まず押さえておきたいのが「108」と「208」です。108は全長約3.5mという超コンパクトサイズですが日本では正規販売されていないため、実際に購入できる最小モデルは「208」となります。
この208はスタイリッシュなデザインと高い実用性を兼ね備え、世界的にも人気のある小型車です。
一方で、人気のある小型モデルと特徴を比較すると、208に加えSUVスタイルの「2008」や安定感を重視した「308」なども候補に挙がります。中でも208は、最新の「3D i-Cockpit」を採用し、直感的な操作性と運転の楽しさを提供してくれる点が大きな魅力です。
つまり、208の魅力と走行性能は小型車の中でも頭ひとつ抜けていると言えるでしょう。
この記事では、「プジョーのコンパクトカー価格とコスパ」、「ハイブリッドモデル208の選択肢」、そして「208 SWのサイズと使い勝手」まで幅広く解説していきます。プジョーの小さい車が気になっている方にとって、次の一台を選ぶヒントになる内容です。
・プジョーの一番小さい車種と日本で選べるモデル
・小型モデル(208・2008・108など)の特徴や魅力
・208の価格帯や中古車購入時の注意点
・ハイブリッドやSWモデルなど選択肢と使い勝手
プジョーの小さい車の魅力とラインアップ

・プジョーで一番小さい車はどれ?
・人気のある小型モデルと特徴
・208の魅力と走行性能
・108のサイズと日本での展開
・コンパクトカーならではのメリット
・小さい車の中でおすすめのグレード
プジョーで一番小さい車はどれ?
プジョーのラインアップの中で「一番小さい車はどれか」と気になる方は多いでしょう。
現行モデルで最もコンパクトな部類に入るのは「プジョー108」ですが、日本市場では現在正規販売されていないため、実際に購入を検討できる小型車としては「プジョー208」が注目されます。
108は全長約3.5mという非常にコンパクトな設計で、街中の狭い道路や駐車スペースにおいて高い利便性を誇りました。一方、208は全長約4m前後と108よりはやや大きいですが、欧州車の中では依然として小さい部類に入り、日本の都市環境にマッチするサイズ感といえます。
このとき重要なのは、単に小さいというだけでなく、車内空間や走行性能とのバランスです。プジョーはコンパクトサイズであってもデザイン性や走行の安定感を損なわず、見た目と実用性を両立させています。
つまり「プジョーで一番小さい車は108、ただし日本で選べる現行モデルでは208が実質的に最小クラス」と覚えておくと良いでしょう。
人気のある小型モデルと特徴

プジョーの小型モデルの中で特に人気が高いのは「208」と「2008」です。208はハッチバックとしてのコンパクトさとデザイン性が際立っており、男女問わず幅広い層に支持されています。
全長約4mのサイズながら、プジョー独自の「i-Cockpit」を採用し、運転席まわりのデザインが直感的で使いやすい点も人気の理由です。
一方の2008はSUVタイプですが、輸入SUVとしては比較的小さいサイズで、日本の住宅街やショッピングセンターの駐車場でも扱いやすい仕様になっています。SUVらしい視界の良さと広い荷室を兼ね備えつつも、都市部での取り回しに優れている点が特徴です。
さらに、308もコンパクトカーとして比較されるモデルですが、208よりやや大きめの設計で、より安定感を求める方に選ばれています。
このように、プジョーの小型モデルは「見た目の洗練さ」「実用性」「運転のしやすさ」をバランスよく備えているため、日本のユーザーにとって魅力的な選択肢となっているのです。
208の魅力と走行性能
プジョー208は、ブランドを代表するコンパクトカーとして世界中で高い評価を得ています。
その魅力はまず外観デザインにあります。ライオンのかぎ爪をイメージしたLEDライトや、曲線と直線を組み合わせたフォルムが、コンパクトでありながら力強い存在感を放っています。
走行性能についても注目すべき点が多くあります。小型ボディならではの軽快さに加えて、最新のプラットフォームを採用することで直進安定性とコーナリング性能を両立しました。
さらにエンジンはガソリン、ディーゼル、EV(e-208)と複数のバリエーションを持ち、ライフスタイルに合わせた選択が可能です。特にe-208は静粛性と加速力に優れ、環境性能と走行の楽しさを兼ね備えています。
また、運転席は「3D i-Cockpit」によって構成されており、小径ステアリングと視認性の高いディスプレイにより、ドライバーが自然な姿勢で操作できる点も大きな魅力です。
つまり208は「小さいのにパワフルで洗練された走りを楽しめる」コンパクトカーとして多くの人に選ばれています。
108のサイズと日本での展開
プジョー108は、全長3,475mm、全幅1,615mm、全高1,460mmほどという非常にコンパクトなサイズで登場したモデルです。軽自動車に近いボディサイズでありながら、輸入車らしい洗練されたデザインを備えている点が特徴でした。
そのため、欧州市場ではセカンドカーや都市用の小型車として高い評価を受けています。
ただし、日本では正規販売が行われていないため、入手するには並行輸入や中古車市場を利用する必要があります。こうした点から国内での流通量は少なく、購入を考える場合にはメンテナンスや部品調達に注意が必要です。
「プジョー108」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 全長 | 約3,475mm |
| 全幅 | 約1,615mm |
| 全高 | 約1,460mm |
| サイズ感 | 軽自動車に近いコンパクトサイズ |
| デザイン | 輸入車らしい洗練されたスタイル |
| 欧州市場での評価 | セカンドカーや都市向け小型車として高評価 |
| 日本での販売状況 | 正規販売なし。入手は並行輸入や中古車市場を利用 |
| 注意点 | 国内流通量が少なく、メンテナンスや部品調達に難あり |
| ポジション | 「プジョーで一番小さい車」として小回りの良さに強み |
| 日本での代替モデル | 208が現実的な選択肢 |
それでも108は「プジョーで一番小さい車」というポジションを持ち続けており、小回りの良さや扱いやすさを重視する方には理想的なモデルといえます。
現在の日本市場では208が現実的な選択肢になりますが、「プジョーの小さい車」に興味を持つ方にとって108は知っておくべき存在です。
コンパクトカーならではのメリット

プジョーをはじめとしたコンパクトカーには、大型車にはない利点がいくつも存在します。まず注目すべきは取り回しの良さです。
全長や全幅が抑えられているため、都市部の狭い道路や細い住宅街でもスムーズに走行でき、駐車スペースも見つけやすいのが魅力です。特に日本の都市環境では車幅が広いと不便さを感じることも多いため、小回り性能の高さは日常生活で大きな安心感を与えてくれます。
また、維持費の面でもメリットがあります。燃費効率が良いモデルが多く、ガソリン代を節約できるのはもちろん、自動車税や保険料も比較的安く抑えられる傾向があります。
さらにプジョーのような輸入車でも、コンパクトカーであれば新車価格が比較的手頃に設定されているため、輸入車デビューの候補としても選びやすいでしょう。
もちろん小型であるがゆえに後部座席や荷室の広さに限界はありますが、その点を割り切れば日常使いや近距離ドライブにおいて大きな不便を感じることは少ないはずです。
デザイン性の高さと走行性能をしっかり両立しているプジョーのコンパクトカーは、日常を快適に彩る一台としておすすめできます。
小さい車の中でおすすめのグレード
プジョーの小型車を検討する際、同じモデルでもグレードによって装備や走行性能が異なります。その中でおすすめされるのは、価格と機能のバランスが取れた「アリュール(Allure)」や「GTライン」などのグレードです。
アリュールは標準装備が充実しており、先進安全機能や快適装備が揃っているため、初めて輸入車を購入する方でも安心して選べます。
「プジョー小型車のグレード比較」
| グレード | 特徴 | 向いているユーザー | リセールバリュー |
|---|---|---|---|
| ベースグレード | 価格が抑えられるが、装備はシンプル | 初期費用をできるだけ抑えたい方 | やや低め |
| アリュール(Allure) | 標準装備が充実、安全機能・快適装備も揃う | 初めて輸入車を購入する方、安心重視 | 高め |
| GTライン | スポーティなデザイン、質感の高い内装、ハイパフォーマンスエンジン選択可 | 走行性能やデザインを重視する方 | 高め |
| 特別仕様車(限定モデルなど) | 専用装備や特別カラーを設定 | 他と差別化したい方、コレクション性を重視する方 | グレードによ |
一方、よりスポーティなデザインや走行性能を求めるならGTラインが適しています。専用のエクステリアデザインやインテリアの質感向上に加え、ハイパフォーマンスなエンジンを選択できるのが特徴です。
走りを楽しみたい方にとっては非常に魅力的な仕様といえるでしょう。
中古車市場でも、これら人気グレードはリセールバリューが高く、安心感があります。もちろんベースグレードも価格を抑えて乗り出せる利点がありますが、装備面で物足りなさを感じることもあります。そのため、快適性や安全性を重視するなら中間グレード以上を選ぶのが賢明です。
小さい車であっても装備や質感にこだわることで、満足度は大きく変わります。
プジョーで小さい車・購入ポイントと価格

・新型プジョー208の値段と価格帯
・コンパクトカーを新車で購入する場合
・208を中古で選ぶときの注意点
・プジョーのコンパクトカー価格とコスパ
・ハイブリッドモデル208の選択肢
・208 SWのサイズと使い勝手
新型プジョー208の値段と価格帯
新型プジョー208は、コンパクトカー市場の中でもデザイン性と走行性能で注目を集めるモデルです。
価格帯はグレードやパワートレインによって幅があり、ガソリンエンジンモデルではおおよそ250万円台からスタートし、上級グレードや装備を加えると300万円前後になるケースが多いです。
さらに、EV仕様の「e-208」を選ぶ場合は価格が一段高くなり、400万円台に達することもあります。ただし、電気自動車はエコカー補助金や自治体の助成金を活用できる場合があり、実質的な負担額は抑えられるケースもあります。
燃料費やメンテナンスコストの低さを考えれば、長期的に見てコストパフォーマンスに優れている点も特徴です。
注意すべき点として、オプションや特別塗装色を選ぶと価格はさらに上がります。輸入車特有の点として、標準仕様に含まれない装備がオプション扱いとなることも少なくありません。
「新型プジョー208」の価格や特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ガソリンモデル価格 | 約250万円台~、上級グレードで300万円前後 |
| EVモデル(e-208)価格 | 約400万円台、補助金利用で実質負担額は軽減可能 |
| 特徴 | デザイン性が高く、走行性能も優秀 |
| コスト面の利点 | EVは燃料費・メンテナンスコストが低く、長期的にコスパ良好 |
| 注意点 | オプションや特別塗装色で価格が上昇しやすい |
| 輸入車の特徴 | 標準装備に含まれない機能がオプション扱いになるケースあり |
| 購入時のポイント | 予算と用途を考え、必要な装備を事前に選択することが重要 |
そのため、購入時には「どの装備が必要か」をあらかじめ考えておくと良いでしょう。新型208は価格以上に満足度の高いモデルであるため、予算と用途を踏まえた選択が重要です。
コンパクトカーを新車で購入する場合

コンパクトカーを新車で購入する場合、いくつか押さえておくべきポイントがあります。
まず新車購入の大きなメリットは、最新の安全装備や燃費性能を備えた状態で安心して乗れることです。輸入車であるプジョーも例外ではなく、衝突被害軽減ブレーキや車線維持支援システムといった先進的な装備が標準化されつつあります。
また、新車は保証期間が長く設定されており、初期不良やトラブルが発生してもメーカーやディーラーによるサポートが受けられる安心感があります。特に輸入車の場合、修理や部品交換にコストがかかることが多いため、保証の充実度は大きな安心材料です。
ただし、新車は中古に比べて初期費用が高額になる点は避けられません。購入後すぐに価格が下がる「初期減価」も考慮する必要があります。
それでも、最新のモデルに乗る満足感や、アフターサービスの手厚さを重視する方にとっては、新車の選択は十分に価値があります。コンパクトカーは価格帯が比較的手頃であるため、輸入車の中でも新車購入に踏み切りやすいジャンルといえるでしょう。
208を中古で選ぶときの注意点
プジョー208を中古で購入する際には、いくつかの重要なチェックポイントがあります。まず確認しておきたいのは修復歴の有無です。
事故車や大規模な修理を受けた車は価格が安い一方で、走行性能や安全性に影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。販売店で点検記録簿を確認したり、信頼できる店舗を選ぶことでリスクを減らせます。
さらに、輸入車特有のポイントとして、定期的なメンテナンスがしっかり行われていたかどうかも大切です。エンジンオイルやブレーキ関連、電装系のトラブルは放置すると修理費用が高額になることが多いため、事前に点検履歴を確認することをおすすめします。
また、走行距離も注目すべき点です。一般的に輸入車は国産車に比べると部品交換のタイミングが早めに訪れる傾向があります。そのため、走行距離が短く、かつ登録からの年数が浅い車両のほうが安心度は高いでしょう。
さらに試乗を通じてシフトの感覚や足回りの違和感をチェックしておくと安心です。とくにセミAT搭載車は人によって操作感に好みが分かれるため、購入前の試乗は必須といえます。
中古の208は新車に比べて価格が手頃で魅力的ですが、見落とすと修理費用がかさむリスクもあるため、慎重に選ぶ姿勢が求められます。
プジョーのコンパクトカー価格とコスパ
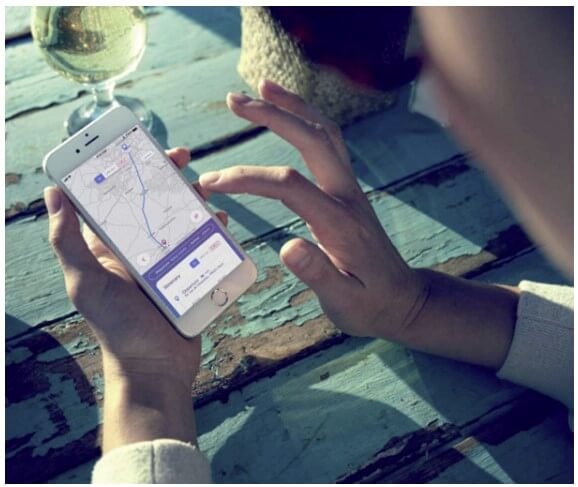
プジョーのコンパクトカーは、輸入車の中でも比較的価格が抑えられている点が特徴です。
例えば208の新車価格はおよそ250万円台からスタートし、上級グレードでも300万円前後に収まります。これは同クラスの欧州車と比較しても競争力のある価格帯です。
一方で中古市場ではさらに価格が下がり、状態の良い車両であっても200万円を切るものも多く見られます。価格面での魅力に加え、燃費性能や安全装備が標準的に搭載されているため、コストパフォーマンスは高いといえるでしょう。
ただし、維持費についても考慮が必要です。輸入車であるため、部品交換や修理の際には国産車より高額になることがあります。しかし、定期的なメンテナンスをしっかり行えば長く乗ることができ、トータルで見れば決して割高とは限りません。
「プジョーのコンパクトカー(特に208)の価格とコスパ評価」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 新車価格 | 約250万円台からスタート、上級グレードでも300万円前後 |
| 中古価格 | 状態の良い車両でも200万円以下が多く、手が届きやすい |
| 価格の特徴 | 同クラスの欧州車と比べても競争力のある水準 |
| 装備・性能 | 燃費性能が良好、安全装備も標準的に搭載 |
| 維持費の注意点 | 部品代・修理費は国産車より高めだが、定期的なメンテで長く乗れる |
| コストパフォーマンス | デザイン性・走行性能・所有満足度を含めると非常に優秀 |
| 購入時のポイント | 新車・中古それぞれの価格と維持費を比較し、ライフスタイルに合った選択をすることが大切 |
むしろデザイン性や走行性能の高さ、所有する喜びを考えるとコスパは非常に優れていると感じられるはずです。新車と中古、それぞれの価格帯と維持費を照らし合わせ、自分のライフスタイルに合った選択をすることが大切です。
ハイブリッドモデル208の選択肢
近年注目を集めているのがプジョー208のハイブリッドモデルです。電動化の流れが進む中で、燃費の良さと環境性能を兼ね備えたモデルとして選ばれる方が増えています。
ガソリンエンジンと電動モーターを組み合わせたパワートレインにより、市街地走行では静かでスムーズな加速を実現し、高速道路でも力強い走りを楽しむことができます。特に短距離での燃費効率が良いため、通勤や買い物といった日常利用に最適です。
さらに、ハイブリッド車はエコカー減税や補助金の対象となる場合があり、購入時の経済的なメリットも見逃せません。ガソリン代の節約効果もあるため、長期的に見れば総合的な維持コストを抑えられるのも強みです。
ただし、バッテリーの寿命や交換費用といった点は注意が必要です。
定期的な点検を怠ると高額な修理費が発生する可能性もあるため、信頼できるディーラーや販売店からの購入をおすすめします。環境性能と経済性を両立した208のハイブリッドは、次世代のスタンダードとして選択肢に入れる価値が高い一台です。
208 SWのサイズと使い勝手

プジョー208にはハッチバックモデルが広く知られていますが、より実用性を重視する方には「208 SW」というステーションワゴンタイプも存在します。
全長がやや延長されているため、荷室容量が拡大され、大きな荷物やアウトドア用品を積み込む際にも余裕が生まれます。コンパクトな車体サイズを維持しながらも積載性を向上させている点は、ファミリー層や荷物を多く運ぶ方にとって大きな魅力といえるでしょう。
走行面では、標準の208と同様に小回りの利く軽快なハンドリングを備えており、街中での取り回しの良さを損なっていません。さらに後部座席を倒せば、荷室を広く活用できるため、旅行や長距離ドライブにも適しています。
サイズ感としては日本の道路事情にもマッチしており、大きすぎず小さすぎない絶妙なバランスです。ただし、流通量は通常のハッチバックに比べて少ないため、中古市場で探す場合は時間をかける必要があります。
デザイン性と実用性を両立させたい方にとって、208 SWは非常に有力な選択肢です。
まとめ:プジョーの小さい車について

・プジョーで一番小さい車は108だが日本では未販売
・日本市場で実質的に最小モデルはプジョー208
・108は全長約3.5mで軽自動車に近いコンパクトサイズ
・208は全長約4mで都市部に適した取り回しの良さを持つ
・小さいサイズでもプジョーはデザイン性と走行性能を両立している
・人気の小型モデルは208と2008である
・2008はSUVながら小型で扱いやすく荷室も広い
・308は208よりやや大きく安定感を重視する人向き
・208はライオンのかぎ爪ライトなど個性的な外観が魅力
・e-208はEV仕様で静粛性と加速力に優れる
・プジョー108は並行輸入や中古市場でしか入手できない
・コンパクトカーは狭い道や駐車に強く維持費も抑えられる
・おすすめグレードはアリュールやGTライン
・新型208の価格帯はガソリン車で250万円台から
・e-208は400万円台だが補助金活用で実質負担を軽減可能


