ホンダ・フリードを検討している多くの方が気になるのが「フリードの荷室寸法」です。特に買い物や旅行、アウトドア、さらにはペットとのお出かけまで、荷室の広さや奥行きはライフスタイルに直結する重要な要素です。
本記事では、「基本的な荷室サイズとは?」という視点からはじまり、「新型フリードのラゲッジスペースは何が進化した?」や「6人乗りと7人乗りでどれだけ荷室が変わる?」といった具体的な比較を通じて、ユーザーの疑問にしっかりと答えていきます。
この記事を読めば、あなたの使い方に最適なフリードが見えてくるはずです。
・フリードのモデルごとの荷室寸法の違い
・6人乗り・7人乗り・5人乗りの荷室活用性の違い
・クロスターやプラスなど特別仕様車の積載特徴
・シエンタとの荷室比較によるフリードの強み
フリードの荷室寸法を徹底比較|モデルごとの違い

・基本的な荷室サイズとは?
・ラゲッジスペースは何が進化した?
・6人乗りと7人乗りでどれだけ荷室が変わる?
・クロスターの荷室はアウトドアで使いやすい?
・プラス(+)と通常モデルの違い
・荷室の寸法と奥行きの目安まとめ
基本的な荷室サイズとは?
ホンダ・フリードの荷室サイズは、そのコンパクトなボディからは想像しにくいほどの実用性を誇ります。
まず、荷室の開口部サイズについて見てみると、高さは約1,110mm、最大幅は1,080mm、地上からの開口部の高さは約480mmとされています。この数値は日常の買い物や旅行、子育て世代のベビーカーの積載など、多くの生活シーンで便利さを実感できるレベルです。
加えて、荷室内の奥行きも重要なポイントです。フリードの場合、3列目シートを使用した状態では荷室奥行きが制限されますが、跳ね上げることで約1,450mmの奥行きを確保できます。このシートの跳ね上げ機構は、道具を積むアウトドア用途や長尺物の収納において非常に役立ちます。
しかもフロアが低いため、重い荷物もラクに載せ降ろしできるのが魅力です。
一方で、フリード+(プラス)など2列シート仕様のモデルになると、奥行きは最大1,600mmにもなり、収納力がさらに強化されます。
フリード 荷室サイズ表
| 項目 | サイズ・内容 |
|---|---|
| 荷室開口部 高さ | 約1,110mm |
| 荷室開口部 最大幅 | 約1,080mm |
| 地上から開口部までの高さ | 約480mm |
| 3列目使用時の荷室奥行き | 制限あり(狭め) |
| 3列目跳ね上げ時の奥行き | 約1,450mm |
| 2列仕様(フリード+)の最大奥行き | 約1,600mm |
| 特徴 | 低床フロアで積み下ろしが容易。3列目は跳ね上げ可能で空間拡張。 |
この差は数字だけ見ると大きく感じないかもしれませんが、実際に自転車やキャンプ用品を積むような場面では、大きな違いとして体感されます。
特に背の高い荷物やペット用ケージを積む人にとっては、開口部の高さやフルフラット対応のラゲッジスペースの有無が大きな評価ポイントとなるでしょう。
ラゲッジスペースは何が進化した?

新型フリードでは、従来モデルと比べてラゲッジスペースの使い勝手が格段に進化しています。見た目の印象だけでなく、実際の収納力や積み込みのしやすさに明確な違いがあるため、旧型からの買い替えを検討している方にとっては要注目ポイントです。
まず注目すべきは荷室の開口地上高。従来モデルでも約480mmと低床設計でしたが、新型ではこの特性を引き継ぎながら開口部の広さと形状が見直され、より荷物の出し入れがしやすくなりました。
特に、荷室の奥行きについては、シートアレンジ次第で最大1,600mm近くまで確保できるため、大きな荷物の積載が可能です。
さらに、新型モデルでは床下収納スペースも拡張されており、奥行き94cm・高さ35cmとかなり実用的な空間が用意されています。このスペースは、工具やアウトドア用品、洗車道具などを収納するのに非常に便利であり、荷物を見せずに積みたいニーズにも応えてくれます。
デザインの面でも工夫がなされており、テールゲートの形状は上部がすぼまった「かまぼこ型」に設計されています。
これにより、駐車場などの狭いスペースでも荷室を開けやすくなっており、都市部での使いやすさも向上しました。こうして見ると、新型フリードは単なるサイズアップだけでなく、細かなユーザビリティに配慮された進化を遂げていることがわかります。
6人乗りと7人乗りでどれだけ荷室が変わる?
6人乗りと7人乗りでは、フリードの荷室スペースに明確な違いが見られます。見た目には大差がないように思えるかもしれませんが、実際にはシート構成の違いが使い勝手に大きく影響してくるのです。
6人乗りモデルでは、2列目にキャプテンシートを採用しています。
これにより、中央の通路が確保されており、ウォークスルーが可能です。このレイアウトの恩恵として、荷室へのアクセスがしやすく、また3列目シートを跳ね上げた際の荷室スペースも効率的に利用できます。
荷室奥行きは約1,450mmまで拡張でき、積載性も高いです。
一方で、7人乗りでは2列目がベンチシートとなり、中央にも乗車スペースがあります。これにより乗車定員が1名分多くなる一方で、シート幅が大きくなるため通路のスペースが狭まり、荷室へのアクセス性やシートアレンジの自由度がやや低下します。
また、3列目シート使用時の荷室奥行きは大きく制限されるため、日常使いでは工夫が必要になるかもしれません。
このように、乗車人数と荷室のバランスをどこで取るかが6人乗りと7人乗りの選択基準となります。家族構成や使用シーンに応じて、自分に合ったシート構成を選ぶことが非常に大切です。
通勤・通学・買い物といった日常使いに加えて、週末のアウトドアや旅行といった用途まで視野に入れた選択が求められます。
クロスターの荷室はアウトドアで使いやすい?
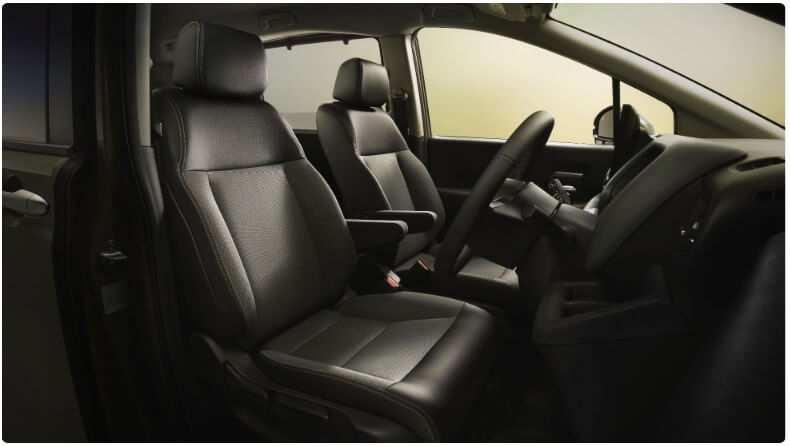
クロスターは、ホンダ・フリードの中でも特にアウトドア向けに特化したモデルです。その特徴的なエクステリアデザインからも分かるように、アクティブなライフスタイルを送る人に最適なパッケージが詰まっていますが、荷室にもそれがしっかりと表れています。
まず、フリードクロスターの荷室サイズは5人乗り仕様で奥行き約1170mm、幅1440mm、高さ1100mmとなっており、十分な収納力があります。3列目を倒せばさらに広く使えるため、キャンプ用具や釣り道具、スポーツ用品なども余裕で積載できます。
特に注目すべきは床下収納の充実度。幅78cm、奥行き94cm、高さ35cmのサブトランクスペースは、アウトドア用品の整理や濡れた荷物の収納に非常に重宝される設計です。
さらに、クロスターには汚れに強い素材が随所に使われているのがポイントです。
ラゲッジ部分も防汚性が高く、水拭きで簡単に掃除できるため、泥だらけの靴や濡れたテントをそのまま積み込んでも問題ありません。この「気兼ねなく使える」点が、アウトドア用途での大きな強みとなっています。
もちろん、低床設計であることも忘れてはいけません。
地上高が約480mmと抑えられているため、重いクーラーボックスやキャンプチェアの積み込みもスムーズです。このような特長から、フリードクロスターはアウトドア志向のユーザーにとって、単なるミニバンではなく、実用性と快適性を兼ね備えた頼もしい相棒となるでしょう。
プラス(+)と通常モデルの違い
ホンダ・フリードには、標準的な3列シート仕様に加えて「フリード+(プラス)」と呼ばれる2列シート仕様のモデルが存在します。どちらも同じ車体をベースにしていますが、荷室空間の設計において明確な違いがあります。
これを理解することは、購入を検討するうえで非常に重要なポイントとなります。
通常のフリードは、最大7人乗りまで対応可能な3列シートを搭載し、ファミリー向けの多人数乗車に最適化された構成です。その代わり、3列目シートを使用する場合は荷室がかなり狭くなり、大きな荷物の積載には工夫が求められます。
3列目を跳ね上げて収納すれば荷室スペースは拡張できますが、それでも床面が完全にフラットにはならず、積載効率にはやや限界があります。
一方、フリード+は2列シート構成を採用しており、3列目シートを持たない分、荷室スペースが非常に広く確保されています。具体的には、荷室奥行きが最大で約1600mmにも達し、開口部地上高も低床設計(約335mm)で積み下ろしが容易です。
また、ユーティリティーボードによって荷室の上下を分けて使うことができ、濡れたものや汚れやすい荷物を分離収納する工夫も可能です。
さらに、床下にも大容量のサブ収納スペースがあり、高さ35cm・奥行き94cmの空間を確保。これらの特徴から、フリード+はアウトドア派や車中泊を楽しみたいユーザーにとって非常に魅力的な選択肢となっています。
つまり、乗車人数の多さを優先するなら通常モデル、積載力を重視するならフリード+という住み分けが自然でしょう。
荷室の寸法と奥行きの目安まとめ

ホンダ・フリードの荷室寸法は、モデルやシート構成によって異なります。そのため、用途に合わせて最適なグレードを選ぶには、各モデルの荷室サイズをしっかりと把握しておく必要があります。ここでは主要なバリエーションにおける寸法の目安を整理してみましょう。
まず、3列シートの通常モデルにおいては、3列目シートを展開している状態での荷室奥行きは約700mm程度とされています。この状態では、日常の買い物やベビーカー程度の荷物なら問題なく積載できますが、大型のスーツケースやアウトドア用品を積むには不向きです。
しかし3列目を跳ね上げて収納すれば、荷室奥行きは約1,450mmまで拡大され、実用性が一気に向上します。
一方で、2列シート仕様のフリード+では、乗車人数を5人に制限する代わりに荷室スペースが最大限に確保されており、荷室奥行きは最大で約1,600mmにも達します。これにより、自転車やキャンプ用品など長尺物の積載も容易になります。
さらに、荷室の幅はモデルを問わず約1,080〜1,260mm、高さは約1,100〜1,255mmとされており、後部開口部の設計にも工夫が見られます。
また、サブトランク(床下収納)にも注目です。新型クロスターやフリード+には、幅78cm・奥行き94cm・高さ35cmの収納があり、見た目以上に多くの荷物を整理して収納することが可能です。車中泊や長距離移動を伴う旅行の際にも重宝するスペースです。
このように、モデルやグレードによって荷室の寸法や使い勝手が大きく異なるため、使い方の優先順位を明確にして選ぶことが求められます。寸法の目安をしっかりと把握することで、自分にとって最も使いやすいフリードを見つけることができるでしょう。
旧型・特別仕様モデルのフリードの荷室寸法ガイド

・初代フリードと現行モデルの積載力の差とは?
・スパイク/スパイクハイブリッドの荷室はまだ実用的?
・プラス4WDモデルの低床設計はどこが便利?
・ハイブリッドモデルの荷室に注意すべきポイント
・GB3・GB5の荷室サイズは現行とどう違う?
・シエンタとの荷室比較で見えるフリードの強み
初代フリードと現行モデルの積載力の差とは?
初代フリード(2008年〜)と現行モデル(2024年以降)を比較すると、車両の基本構造はキープコンセプトでありながら、細かな点で大きく積載力が進化していることがわかります。両者は同じ「コンパクトミニバン」というカテゴリに属していますが、実際の使い勝手には違いが明確に存在します。
初代フリードは、当時としては画期的なパッケージングを採用しており、3列シートでありながら全長約4.2mという取り回しの良さを実現していました。
荷室の奥行きは最大でも約1,300〜1,400mm程度とされており、3列目シートを跳ね上げた際にも完全なフラット構造にはならなかったため、大型荷物の積載には限界がありました。また、床下収納の概念も薄く、収納力を補う装備は限られていた印象です。
これに対して、現行モデルでは、ラゲッジルームの設計が抜本的に見直されており、使いやすさが飛躍的に向上しています。
特に2列シート仕様のフリード+やクロスターは、荷室奥行きが約1,600mmにまで達し、収納力において初代を大きく上回ります。加えて、床下収納の容量や設計も進化し、サブトランクを活用することで荷室全体の容積が大幅に増加しています。
さらに、現行モデルでは荷室開口部の形状が工夫されており、開口高や開口幅も拡大されているため、荷物の出し入れがよりスムーズです。開口地上高も低く設計されているため、重い荷物を持ち上げる際の負担も軽減されています。
こうして比較してみると、初代フリードは「ミニバンとしての最低限の機能を満たすモデル」だったのに対し、現行モデルは「積載性を軸に進化した実用車」と言えるでしょう。
スパイク/スパイクハイブリッドの荷室はまだ実用的?

ホンダ・フリードスパイクおよびフリードスパイクハイブリッドは、2010年代前半に登場した2列シート専用モデルで、ラゲッジスペースを重視した設計が当時高く評価されました。では現在においても、それらの荷室は実用的と言えるのでしょうか?
結論から言えば、日常使いや軽めのアウトドア用途であれば、今でも十分に実用性を感じられるレベルです。フリードスパイクの最大の特徴は、2列シートで完全フラットな荷室スペースを確保している点です。
後部座席を畳めば奥行き約1,600mm、幅1,090〜1,180mm、高さ1,000mm程度の空間が出現し、車中泊や小型の家具を運ぶなど、様々なシーンに対応できます。
さらに、荷室にはユーティリティーボードやフックが備えられており、荷物を整理して積む工夫もしやすい構造となっています。この機能性は、現行のフリード+に近いものがあり、10年以上経った現在でも色あせていません。
ただし、床下収納は新型モデルと比べると狭く、荷物を隠して収納したいというニーズにはやや不向きな印象もあります。
また、ハイブリッドモデルであっても、燃費は現行e:HEVに比べて劣る傾向があり、運転支援システムも今の基準では物足りない部分があるでしょう。そのため、安全装備や低燃費性能を重視するユーザーには新型モデルを推奨します。
とはいえ、価格面で中古市場では手頃に購入できることや、シンプルな構造によるメンテナンス性の良さから、実用性重視のセカンドカーとしては今なお有力な選択肢です。ライフスタイルに応じた用途が明確であれば、スパイク系モデルは今でも十分に「使える」1台と言えるでしょう。
プラス4WDモデルの低床設計はどこが便利?
フリードプラスの4WDモデルは、低床設計が大きな魅力のひとつです。
一般的に4WD車は駆動系の構造上、床面が高くなりがちで、荷室の高さや使いやすさに影響が出ることがあります。しかし、ホンダのフリードプラス4WDは、そうした常識を覆すような低床設計を実現しています。
具体的には、荷室の開口部地上高が約335mmと非常に低く、これは大きくて重たい荷物の積み降ろしを行う際に、体への負担を大幅に軽減してくれます。
特に高齢者の乗降や、アウトドアグッズ・ペットケージ・自転車といった長尺で重量のあるアイテムを扱うユーザーにとって、この高さの低さは日常の快適さに直結します。例えば、キャンプで使用するクーラーボックスを車に載せるとき、わずかな段差でも腰への負担が変わります。
その点でフリードプラスの低床は、荷物の積載に不慣れな方にもやさしい設計です。
また、床が低いということは、車中泊などの用途にも有利に働きます。寝転んだときの天井までの余裕が増え、狭苦しさが軽減されるからです。ただし注意点もあります。
4WD仕様になることで一部の収納スペースが狭くなっていたり、燃費性能が若干低下する傾向にあるため、トータルのバランスを見ながら選ぶことが大切です。積載性と走破性、両方を求める方にとって、フリードプラス4WDの低床設計は非常に実用的な選択肢だといえるでしょう。
ハイブリッドモデルの荷室に注意すべきポイント

フリードのハイブリッドモデルは、燃費性能と静粛性に優れたe:HEVシステムを搭載しており、都市部から長距離移動まで快適にこなせる点が大きなメリットです。しかし、荷室に関してはひとつ注意しておきたいポイントがあります。
それは、バッテリーの搭載位置による床下スペースの制限です。
通常のガソリンモデルであれば、荷室下に設けられたサブトランク(床下収納)を自由に活用できます。キャンプ道具や掃除道具、スペアタイヤ、工具などをスッキリと収めることが可能です。
ところがハイブリッドモデルでは、このスペースの一部にバッテリーユニットが配置されているため、床下の容量が限定されるケースがあります。特にフリード+やクロスターのようなアウトドア用途を想定している方にとっては、荷物の収納計画に影響を及ぼす可能性があります。
また、ハイブリッドの重量増によるリアサスペンションへの負荷も見逃せません。
重たい荷物をフル積載した状態で長距離走行をすると、ガソリンモデルと比べて若干の沈み込みを感じることがあるという声も一部あります。ただし、これは日常利用において大きな支障になるレベルではありません。
その一方で、ハイブリッド特有の回生ブレーキシステムにより、積載物の滑りにくさが向上していると感じるユーザーもおり、細かな点での使い勝手には差が出ています。このように、ハイブリッドモデルの荷室にはメリットと注意点の両面があるため、自身の使用目的と照らし合わせながら検討することが大切です。
GB3・GB5の荷室サイズは現行とどう違う?
ホンダ・フリードの過去モデルである「GB3」および「GB5」は、それぞれ初代(2008年〜)と2代目(2016年〜)にあたる型式です。どちらも当時としては高い実用性を誇っていましたが、現行モデルと比較するといくつかの違いが見えてきます。
ここでは特に「荷室サイズ」にフォーカスして、その差を明確にしてみましょう。
GB3(初代モデル)の荷室は、3列シート車としての必要最低限のスペースを確保しており、奥行きは約1,200〜1,400mm程度が目安とされています。
シートを倒せばフラットには近づきますが、完全な段差ゼロではなかったため、大型の荷物や長尺物を積む際には一工夫必要でした。また、開口部地上高が約480mmと、当時の他ミニバンと比較するとやや高めだった点もネックとなっていました。
フリード GB3とGB5の荷室比較
| モデル | 販売時期 | 荷室奥行き | フラット化 |
|---|---|---|---|
| GB3(初代) | 2008年〜 | 約1,200〜1,400mm | 段差あり、完全なフラット不可 |
| GB5(2代目) | 2016年〜 | 最大約3,045mm(室内長) | ほぼフラットだがわずかな段差あり |
次にGB5(2代目)は、GB3よりも室内長が最大約3,045mmまで拡大され、セカンド・サードシートのスライドや跳ね上げによって、フレキシブルな荷室アレンジが可能になっています。
ただし、2列目と3列目の間にわずかな段差が残る点や、荷室の横幅が大きく広がっていなかった点など、今のフリード+やクロスターに比べると実用性には限界がありました。
現行モデルでは、特に2列シート仕様のフリード+において荷室奥行きが1,600mmを超え、開口地上高も大きく下がったことで、積載性が飛躍的に向上しています。これに加え、下部収納の広さやフルフラット構造の採用により、車中泊や大型の荷物にも対応しやすくなっているのです。
つまり、GB3・GB5は当時のニーズには応えたモデルでしたが、現代のフリードはそれを大きく超える進化を遂げたと言えるでしょう。
シエンタとの荷室比較で見えるフリードの強み
トヨタ・シエンタとホンダ・フリードは、どちらもコンパクトミニバン市場で人気を二分するライバル車です。両者のボディサイズや居住性は似通っていますが、荷室に関しては微妙な差が性能や使い勝手に影響を与えています。
特に5人乗り仕様での荷室比較を通じて、フリードの強みがより鮮明になります。
まずシエンタの荷室寸法は、長さ2045mm×幅1265mm×高さ1055mmとされています。これは非常に優れたスペックで、車中泊やアウトドアシーンでも十分に通用する設計です。
一方、フリードクロスターの5人乗り仕様では、長さ1970mm×幅1260mm×高さ980mmと、若干のサイズ差があります。しかし、注目すべきは「使える空間」の質です。
フリードは荷室に無駄な張り出しが少なく、床下収納が非常に広く設計されているため、実際の積載量においては見た目以上の余裕を感じられます。例えば、サブトランクの奥行きが約94cm・高さ35cmあり、シエンタにはない収納力を備えています。
また、開口地上高が低く、荷物の積み降ろしも容易です。さらに、フリード+ではユーティリティーボードの活用によって荷室を上下に分けて使うことができ、汚れ物や濡れた荷物の仕分けにも便利です。
一方でシエンタはハイブリッドモデルでしか4WDが選べないという制限があるのに対し、フリードはガソリン・ハイブリッド両方で4WDを選択できる点も強みとなります。
つまり、スペック上の寸法だけでなく、実際の積載のしやすさ、拡張性、使い勝手においてフリードは高い評価を得るに値するモデルだといえるでしょう。
まとめ:フリードの荷室寸法について

・フリードの荷室開口部は高さ約1,110mm・幅1,080mm・地上高480mm
・3列目を跳ね上げれば奥行き約1,450mmの荷室が確保できる
・フリード+は奥行き最大1,600mmで積載力が高い
・新型モデルは床下収納が拡張され奥行き94cm・高さ35cmの空間を持つ
・新型クロスターは「かまぼこ型」テールゲートで開閉しやすい
・6人乗りはキャプテンシートで荷室へのアクセス性が高い
・7人乗りはベンチシート採用で乗車人数優先の設計
・クロスターは防汚素材を使用しアウトドアでの使用に適している
・フリード+はユーティリティーボードで荷室を上下に分けて使える
・荷室の幅はモデルにより1,080〜1,260mm、高さは約1,100〜1,255mm
・初代フリードの荷室は現行より小さく床下収納もなかった
・スパイクは今でも1,600mm級の荷室奥行きで実用性が高い
・4WDモデルでも開口部地上高が約335mmと低床設計を維持
・ハイブリッドは床下収納がバッテリーで狭くなる点に注意
・シエンタに比べてフリードは床下収納が広く4WDの選択肢も多い
・フリードの寸法図で比較する室内空間と外寸の特徴・最適なグレード
・フリードの最小回転半径は大きい?旧型・シエンタや他車との違い
・フリードの鍵の電池はどこで買える?電池交換の時期と手順を解説
・フリードは何人乗りが人気?家族構成別に最適なグレードの選び方
・フリードのワイパーゴム適合表、初心者向け交換方法と購入先


